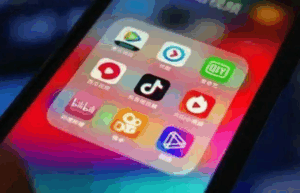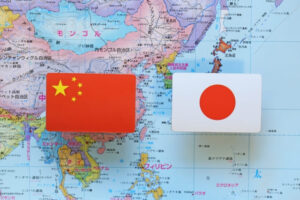日本では幹細胞治療は、がん治療などの医療領域や、若返りのための美容医療として、実用的な治療方法の1つとして採用されています。
その幹細胞治療は中国でも、大きく注目されてきています。
幹細胞治療の開発者は日本であり、同時に研究・実用面で世界のパイオニアであるため、中国だけでなく世界から注目されています。
そこで、本記事では、幹細胞治療の中国現状、中国における日本医療の人気、チャンスの活かし方、中国ビジネスの最新成功事例まで一挙に紹介します。
幹細胞治療の中国現状

ではなぜ、幹細胞治療が大きく注目されるようになったのかについて、中国の幹細胞治療の歴史をさかのぼりながら探っていきましょう。
無秩序時代(~2012年)─ビジネス化が先行してしまった医療現場
2000年代初頭、中国でも幹細胞研究が急速に進みました。
実際に、北京大学が2002年に研究センターを設立し、2004年には中国初のヒト胚性幹細胞(不死性でほぼ無限の発生能力を持つ細胞)の培養に成功します。
しかしながら、「治療法の開発」よりも「ビジネス化」が先行し、ある事件が起きました。
そのある事件とは、2012年に魏則西(ウェイ・ズーシー)さんという学生が、無許可の免疫細胞治療(幹細胞治療と宣伝)を受けた後、がんで亡くなったという事件です。
しかも治療費は20万元(約400万円)も請求されていたのです。
この事件がきっかけとなり、中国政府は全国の幹細胞臨床研究を全面的に停止しました。
「治療と称した金儲け」が蔓延していた実態が明るみに出てしまったのです。
ルール作り時代(2015~2020年)─「特区」で安全な実験を開始
2015年に中国で幹細胞治療が再スタートします。
政府は厳しい基準を設け、幹細胞治療を「第三類医療技術」(高リスク医療)に指定し、限られた場合の使用を認めます。
具体的には、以下の条件を課しました。
〇実施機関は三甲医院(最高ランク病院)に限定
〇中国倫理委員会の二重審査に合格することが必須
さらに、2018年に最も大きな転機が訪れます。
それは、中国海南島・博鰲(ボアオ)楽城に「医療特区」が作られたことです。
その海南島の「医療特区」のルールは、以下の通りです。
〇海外で承認済みの未承認治療を導入可能
〇免税措置で医療機材輸入が容易に
それまで中国で幹細胞治療が厳しく制限されてしまったため、無許可で幹細胞治療を行う「闇治療」が横行してしまいました。
幹細胞治療に対する規制緩和は、「闇治療」に対抗した政策でもあったのです。
産業化時代(2021~2025年)─初の承認と価格透明化
2025年1月には、ついに幹細胞治療の国産薬が誕生します。
長い研究期間を経て、ついに中国初の幹細胞薬が登場したのです。
その薬品名は、アイミーマイトサイ注射液(中国語:艾米迈托賽注射液)というもので、価格は1回1.98万元(約4万円)でした。
当時、その価格が米国同等薬品の1/60の価格という破格の設定だっため、世界を驚かせました。
その狙いは、価格公示することで、「闇市場」と決別する目的も含まれており、さらに、海南特区に踏み込んだ改革も行われました。
「膝関節症治療:3.6万元/回」や「肝機能再生療法:8万元/コース」というように、低価格でかつその価格もすべてオープンになります。
治療費を公式に公開することで、高額な闇治療との差別化を図りました。
直近─「日本連携」がカギに
直近では、新政策という追い風が吹きます。
海外の治療法導入する際、従来は3年以上かかっていましたが、最短3か月で導入が可能に。
また、深セン・香港に近い南沙地区に、日中の共同研究拠点の整備を進めています。
残る課題はまだまだあり、闇市場が未だ存在していることや、日本技術への依存が重大課題と認識されています。
現在、中国は「日本との協業で世界標準を目指す」過渡期にあります。
中国海南の病院では既に、日本の再生医療技術を導入した治療が行われ、中国富裕層から注目を集めているのです。
依然として注目されている日本医療

中国での幹細胞治療が大きく発展を遂げている今、未だに日本医療に人気があります。
なぜ日本での治療に人気があるのでしょうか?
日本医療が選ばれる理由は主に3つあります。
それは、「信頼」「技術」「心」の3つです。
理由1:揺るぎない「信頼性」—医療制度と透明性が医師への信頼性に影響
日本医療の信頼性は、世界保健機関(WHO)の医療評価で世界1位(2022年)に選ばれた事実が物語っています。
その背景には、他国にはないユニークな制度設計があります。
その1つが国民皆保険制度です。
国民皆保険制度では、全住民が医療費の自己負担30%で高度医療を受けられます。
月額8万円を超える分は全額免除されるため、がん治療など高額療養でも破産リスクがありません。
医者からすると、国家が医療費を負担してくれるため、患者の金銭状況を判断して、意図的に本来受ける必要のない治療を実施するモチベーションは起きません。
2つ目のユニークな制度として、医療費の透明性があります。
薬価や治療費が公定価格で規制され、病院ごとの随意値上げが禁止されています。
さらに医師の収賄には厳罰が科され、謝礼金のような慣行も存在しません。
一方、中国にはこれらのような制度がありません。(中国医療制度はあるが、自己負担率が相対的に高い)
その結果、中国では医師に『心付け』を渡さないと真剣に診てくれません。
日本の病院では費用明細から治療リスクまでオープンで隠さず説明してくれますが、中国の病院では『心付け』の慣習があるため、不透明感が未だに存在しているのです。
こうした中国医療の不透明感が、中国医師や治療の信頼性に悪影響を与えているのです。
理由2:革新と実用性を兼ねた「技術力」——早期発見から再生医療まで
日本の医療の強みは「早期発見」にあります。
例えば、肺がんでは80~90%が中早期で発見され、全体の5年生存率は66.2%(中国は40.5%)とアジア最高水準です。
これを支えるのが、画期的な検査技術です。
例えば、Micro CTC(Circulating Tumor Ceiis、血中循環がん細胞)検査では、採血だけで全身のがんリスクを評価します。
わずか0.5mmの微細ながん細胞を85%の感度で捕捉し、94.45%の高精度で「陰性」判定を出せます。
PET-CT(positron emission tomography、陽電子放出断層撮影)/MRI普及率も人口100万人あたりの保有台数が世界一です。
結果として、精密画像診断が日常的に実施可能なのです。
再生医療も世界のパイオニアであり、細胞レベルで人生を変える技術が得意です。
具体的には、iPS細胞(体の細胞に特定の遺伝子を導入し、受精卵に近い状態に戻すことで、さまざまな細胞に分化する能力と無限に増殖する能力を持つ細胞)技術を軸に、日本は再生医療のグローバル拠点となっています。
iPS臨床試験数は86件を推進しており、世界1位です。
実用化事例でも、京大提携クリニックが、iPS細胞を用いた関節軟骨再生治療(成功率92%)を開発しました。
ヘレネクリニックでは、幹細胞で肝機能を90日間で25%回復させる「細胞カクテル療法」を開発しています。
理由3:「患者中心」のケア哲学——ホスピタリティ
日本医療が選ばれる理由の3つ目は心、つまりホスピタリティです。
具体的には、診療プロセスの細やかさ、言語の壁を越える仕組みです。
診療プロセスの細やかさ
診療プロセスの細やかさは世界一です。
まず、説明が非常に丁寧であることに、中国人は感動を覚えます。
診断結果を図解付きで説明し、疑問点は時間をかけて解消するスタンスは、中国にはあまりありません。
また、日本医療における精密検査の代表である胃カメラは、鼻腔挿入式を採用し「苦痛ゼロ」を追求しています。
診療プロセスでの苦痛を最小限に抑えようという努力が垣間見えます。
言語の壁を越える仕組み
日本医療のホスピタリティを感じるもう1つの特徴は、言語の壁を越える仕組みです。
国際的な多くの日本クリニックでは、医療コーディネーターサービスがあります。
ビザ取得・通訳・宿泊手配まで一括支援してくれます。
このように、日本医療が選ばれる本質は、技術や制度だけではありません。
「患者の人生と真摯に向き合う姿勢」が、国境を越えた信頼を生んでいると言えるでしょう。
中国ビジネスへの応用の具体策—3つの成功モデル実践ガイド

日本医療サービスが中国で人気な状況下で、中国の幹細胞治療の人気が上昇しているのですから、医療ビジネスとして、このチャンスを活かさない選択肢はありません。
ここからは、幹細胞治療医療サービスの中国市場の攻略方法について、紹介したいと思います。
中国政策特区をフル活用
中国海南島の南端に位置する博鰲(ボアオ)楽城に、国際医療ツーリズム先行区があります。
ここは「医療のシリコンバレー」と呼ばれ、日本の医療機関にとって大きなビジネスとなっています。
なぜなら、海外未承認の先進医療を最短3か月で導入できる特別ルートがあるからです。
医療法人社団医進会の小田クリニックは、真っ先にこのビジネスチャンスをつかんだ先駆者です。
小田クリニックは、NK細胞(ナチュラルキラー細胞、免疫細胞の一種)治療技術を持っていましたが、中国進出の壁に悩んでいました。
突破口となったのは、中国現地パートナー・済民医療との出会いでした。
済民医療は、小田クリニックと戦略・技術パートナーとして迎え、中国海南島に「博鰲国際病院」を立ち上げます。

【博鰲国際病院】
具体的に、小田クリニックは、「技術ライセンス供与」と「臨床応用とコア技術の移転」「共同開発」「培養試薬の中国国産化」を博鰲国際病院にて展開しています。
技術ライセンス供与
小田クリニックは、NK細胞療法、NKT細胞免疫療法、幹細胞療法などの独自技術を、博鰲国際病院に提供しています。
臨床応用とコア技術の移転
技術移転には、医師研修や医療品質管理の責任が含まれますが、博鰲国際病院から年間技術サービス料を受け取っています。
共同開発
また、博鰲国際病院は、スイスなどから幹細胞治療のトップ医療施設と協業し、各国の医師と小田クリニックで共同研究開発も行っています。
具体的には、免疫調節、抗腫瘍、抗衰老分野を中心に、細胞治療技術の改良(例:NKM改良療法)や外泌体応用の共同研究を推進しています。
培養試薬の中国国産化
培養試薬の中国国産化も大きく進めています。
小田クリニックの核心技術である細胞培養基、NKMシリーズ試薬、高濃度培養バッグを中国国内で生産・販売されています。
中国国内細胞治療市場の成長を見込み、コスト削減と供給安定化を図っているのです。
具体的な協業内容については、下記でもご覧になれますので、興味のある方はご覧ください。
1218042109.PDF (cninfo.com.cn)
中国SNSの活用
中国市場への参入方法として、中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)などの中国SNSの活用が一般的です。
ところが、医療関連情報の規制が厳しく、直接的な宣伝が困難です。
最近では、こうした課題を逆手に取り、中国人旅行客を効果的に集客する方法が確立されています。
規制の厳しい中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)では、美容医療を旅行コンテンツに織り込む手法が突破口になります。
例えば、中国人人気インフルエンサー「西资卡」さんは、日本旅行の動画の中で、観光スポット紹介の合間に美容クリニックをさりげなく登場させました。
施設の清潔さや医師の丁寧な対応に焦点を当て、「観光のついでに受けられる健康チェック」と自然にアピールしたのです。
この際のポイントは、規制ワードを回避することです。
「治療」ではなく「体質改善」や「身体のメンテナンス」といった表現を使い、動画の前半は観光コンテンツを主体に構成します。
投稿後は、インフルエンサーと個別契約を結び、フォロワー向けにDMでクリニックの正式リンクを共有する仕組みです。
あるクリニックでは、この手法で予約問い合わせが30%増加しました。
中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)以外にも選択肢があります。
例えば動画プラットフォーム「BiliBili(ビリビリ)」は医療コンテンツの規制が比較的緩やかです。
名古屋の歯科医院は、抖音で削除された矯正治療の動画を「歯並びと顔のバランス」に焦点を変えてBiliBiliに再投稿し、月間数万回の再生を達成しました。
「正しい歯磨き法」といった広告とみなされないテーマから始めるのも効果的です。
中国SNS活用の詳細は、下記記事でも紹介していますので、興味ある方はご覧ください。
医療業界必見、中国人旅行客を獲得する秘訣 | CRESON Media | 中国SNS動画・越境EC支援のクレソン
仲介機関との提携で信頼を構築
インフルエンサー活用だけでは限界がある場合、中国現地の仲介機関との連携が有効です。
これらの機関は患者の事前審査(健康状態や支払い能力)を行い、日本側は施術に専念できます。
仲介報酬は比較的高めに請求されることが多いですが、中国市場では標準的な水準です。
ある美容医療機関では、このモデルで初期費用を抑えつつ中国人患者数を2倍に拡大できました。
注意すべきは提携先の厳選です。
虚偽広告を行う業者も存在するため、過去の実績や顧客評価を必ず確認しましょう。
信頼できる仲介機関を見つければ、現地のニーズに合った患者を効率的に獲得できます。
中国語サイトのSEO対策を強化
中国人旅行客の半数以上は渡日前に情報収集します。
ここで鍵となるのが、SEO対策と利便性を備えた中国語サイトです。
具体的には次のステップで効果を高められます:
①検索キーワードの最適化
「沖縄 長寿医療」「東京 がん検診」のように「地域名+サービス名」を組み合わせたキーワードを選定します。
②オンライン相談システムの導入
AIチャットボットで24時間対応し、症状に基づいた検査プランを自動提案可能になります。
ある医療機関では、問い合わせから予約までの時間を50%短縮できました。
③デジタル化されたアフターケア
検査結果を中国語のPDFと解説動画を作成し、WeChat経由で送信すれば、帰国後も継続的な健康管理をサポートできます。
これらの施策を組み合わせたあるクリニックでは、中国語サイトの月間アクセス数が3倍に増加しています。
最後に

今回の記事でご案内した内容は、あくまで現時点の弊社の分析に基づくものです。
実際に自社ブランド商品を売り込みたい場合は、自社ブランドの特徴や中国市場状況に合わせて、マーケティングを行うことがおススメです。
弊社は現在、中国版TikTok抖音(Douyin)・RED(小紅書)を活用した中国SNSの運用代行や、中国への越境ECの支援などのサービスを展開しております。
ぜひご気軽にご相談ください。